こんにちは、あしあです。
先日、展覧会『祇園祭〜鷹山復興記念展〜』(京都文化博物館)と『鷹山復活写真展 写真家大道雪代』(鷹山会所西隣)を見てきました。
展覧会の詳細はこちら↓
3年ぶりに山鉾巡行が行われた2022年祇園祭。なかでも話題になっていたのは「鷹山」の復帰でした。
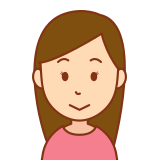
「鷹山の復活はどのくらい意義あることなの?」
こんな疑問に、展覧会で見てきたことをもとにお答えします。
「鷹山」の特徴

まずはじめに、鷹山の基本情報をまとめておきます。
- 所在地は衣棚町(三条通新町付近)
- 鷹狩の名手・在原行平(伊勢物語で知られる在原業平の兄)が鷹狩をする場面を題材にした山
- 御神体は鷹遣(たかつかい:鷹を手に持つ)、樽負(たるおい:樽を背負う従者。粽を食べるカラクリ人形)、犬遣(いぬつかい:犬を引いている)の3体
- 松の枝に獲物の雉(キジ)がとまっている(鷹ではない)
鷹山復活の意義
結論から申し上げると、鷹山の復興は、
コロナ禍の困難な時代を生きる私たちに希望を与えてくれる存在であると同時に、
災害や紛争から文化財を守っていくことの大切さを教えてくれる存在であると実感しました。
大昔の鷹山は、かなり発展した山鉾だったようです。
鷹山復興記念展で公開されている資料「祇園御霊会細記事」に描かれた絵から、江戸時代中期ごろの、元気に巡行に参加している鷹山の姿が確認できます。
鷹山が最後に山鉾巡行に参加したのは1826年(江戸時代)。
その年の巡行中の大雨によって懸想品が汚れてしまい、翌年から参加しなくなりました。
また、1864年の蛤御門の変(禁門の変)で山車(だし)がほとんど焼けてしまいました。
その後は宵山に奇跡的に残った人形を飾ることで祭りに参加してきました。
鷹山を世話していた町では、巡行復帰への希望の灯は途絶えていなかったようで、鷹山復興記念展では、鷹山の飾り付けに関する覚書や詳しい絵画資料を多数見ることができました。
復興の話は、昭和時代に何度か持ち上がったそうですが、資金や運営面の困難さで実現しませんでした。
1990年前後に復興の話が再度持ち上がるも、具体的に動き出したのは2012年以降のようです。
10年もの準備期間を経てようやく今年、196年ぶりの巡行復帰を果たしたのです。
一度失われたものを元に戻すには相当な時間と労力が必要なんですね。
だからこそ、文化財を保護していく活動の価値を実感しました。
近年の復興の歩みをまとめておきます。
- 2014年:祇園囃子を演奏する囃子方が結成され活動を始める。
- 2015年:鷹山保存会が発足。
- 2016年:出囃子を披露。子どもたちの練習も本格的に。
- 2017年:菊水鉾より櫓(やぐら)の寄贈を受ける。
- 2018年:船鉾より車輪の寄贈を受ける
- 2019年:「唐櫃巡行」という形で巡行に参加
- 2021年:代表者が拝礼巡行に参加。懸想品がほぼ完成。
- 2022年:山鉾巡行に復帰!
将来個人的に期待しているのは、カラクリ人形の復活です。
もし実現すれば、蟷螂山のように後祭の人気山になりそうですよね。
これから鷹山が「令和の山」として繁栄していく様子をともに見守っていきましょう。
鷹山を応援したい方は、寄付という形で支援もできます。
興味ある方は調べてみてください。
最後まで読んでいただきありがとうございました!
あしあより







コメント