アートで心を動かして、人生を豊かにしよう!
今回行ってきた展覧会はこちらです!
『歌と物語の絵 -雅やかなやまと絵の世界』
2023年6月から泉屋博古館(京都・鹿ヶ谷)にて開催されました。泉屋博古館所蔵品(住友コレクション)の歌絵と物語絵を紹介する展覧会で、コレクション展としての一面も備えていました。
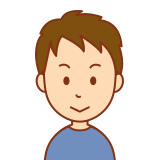
泉屋博古館のコレクション(住友コレクション)の特徴は?
実は、泉屋博古館のコレクションは、中国古銅器をはじめとした東洋の美術工芸品が中心です。一方で、日本絵画も優れた作品を収蔵しているので見どころが多く、京都でおすすめの美術館です。
本展のために選ばれた収蔵品は、文学と相互に喚起し合う「やまと絵」の性格が浮かび上がるものでした。やまと絵の魅力を知る良い機会だったと思います。
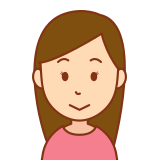
やまと絵の楽しみ方が分からない……
そんな方のために、この記事では、実際に展覧会に行ってみて興味深かった作品を5つ選んで紹介します。
あくまで私が個人的に気になった作品なので、感想が違うところもあると思いますが、楽しんで読んでもらえたらと思います。
この記事を読むことで、やまと絵の楽しみ方を知り、あなたの美術鑑賞を充実させる一助となれば嬉しいです。
早速ですが、今回私が選んだ作品はこちらです。順番に解説していきます。
企画展「歌と物語の絵」(泉屋博古館)の面白い絵5選

伝 土佐広周《柳橋柴舟図屏風》江戸時代17世紀(泉屋博古館蔵)
川辺の橋。
大きくて立派な橋なのに、人が不在で不自然です。柴を積んだ舟も無人。なぜだと思いますか?
それは、和歌で詠まれる観念的な世界を描いているからです。「橋」「柳」「水車」は、いずれも宇治を表す歌枕。
和歌の世界では、「宇治」は「憂し」という言葉と結びつき、世を憂いた者の隠棲の地として、物悲しくも美しいイメージが定着していました。
橋は浄土への架け橋、水車は輪廻転生の象徴で、順に新芽・若葉・青葉・落葉の姿で描かれた柳が四季の移ろいを表しています。
昔の人が浄土思想に強く影響を受けていたことがうかがえる図屏風です。今でも日本各地に数多く残っている「浄土庭園」にも通じるものがありますね。
伝 土佐永春《是害房絵巻》南北朝時代14世紀(泉屋博古館蔵)
人間の腕と脚が生えた鳥が登場する物語。
絵面が奇妙で、その時点でもう面白い。
この鳥人間は、どうやら唐の天狗のようです。パッとみて分かるのは湯治を受けている場面。漫画のように天狗のつぶやきが添えられて、コミカルな感じですが、重要文化財でもあります。
調べてみると、『今昔物語』に取材した作品で、仏教先進国(唐)の天狗が日本の僧に法力比べをしにやって来たら、手痛いしっぺ返しをくらった、といったストーリーでした。
いわゆる「天狗になることへの戒め」が説かれているのでしょうか。仕事や人間関係における教訓として受け取りたい絵巻です。
宗達派《伊勢物語図屏風》桃山〜江戸時代17世紀(泉屋博古館蔵)
言わずと知れた恋多き男の物語に取材した図屏風。
男女のすれ違いなど、共感できる点も多い恋愛の場面を、人間味あふれる表情や仕草で描かれています。
寛容で、おおらかで、作者の人間に対する愛が感じられます。恋愛する人を温かく応援しているような感じが全体から伝わってくる作品です。
《源氏物語図屏風》江戸時代17世紀(泉屋博古館蔵)
『源氏物語』54帖のうち、「桐壺」「若葉」「紅葉賀」「絵合」「葵」「胡蝶」など12場面を抜き出して描いています。
場面の選定や配置は、物語の流れというよりむしろ、季節や内容など全体のバランスを重視して決められていて、デザイン性が感じられます。
登場人物の表情や行動を見ていて面白いのは、高貴な雰囲気や上品さをやや落として描かれていることです。題材は古典の格調高い恋愛文学ですが、テレビドラマを見ているような親しみやすさが感じられます。
江戸時代初期の絵師で風俗画を得意とした岩佐又兵衛の工房作とされています。
狩野常信《紫式部観月図》江戸時代18世紀(泉屋博古館蔵)
紫式部が石山寺(現在の滋賀県大津市)で『源氏物語』を書き始めた場面です。
湖面に映る十五夜の月が印象的に描かれています。
不朽の恋愛物語が生まれる瞬間。
2024年放送予定の大河ドラマ「光る君へ」でも描かれそうなシーンですね。
江戸時代の狩野常信による作品ですが、数多くの画家が描いてきた主題です。いろんな作品に出会って、画家ごとの違いを楽しみたいですね。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
みなさまもぜひ自分のお気に入りのやまと絵を見つけてください。
今回取り上げた『源氏物語』を読んで、恋愛についての教養を深めたい方は、こちらの記事も参考にしてみてください。
最後までお読みいただきありがとうございます。
このブログは、ミュージアムや展覧会のさまざまな活用法をお届けしているブログです。
Instagramもやっています。有意義な情報、有益な情報を投稿していきますので、ぜひフォローをお願いします。
Instagram →tasuku(@tasukuasi.museum)





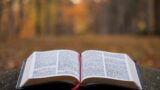


コメント