アートを見て心を動かそう!本日の展覧会はこちら!
「ピカソとその時代 ベルリン国立ベルクグリューン美術館展」
2023年2月から国立国際美術館(大阪)にて開催された展覧会です。(国立西洋美術館(東京)から巡回)
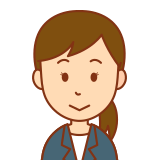
ピカソの絵ってよくわからない……
そんな声を聞くことがあります。私も、初めてピカソの絵を見たとき、そう思いました。
それでも、なぜか心に残る力がありませんか。「ピカソとその時代」展は、その疑問について考える良い機会でした。ピカソの作風をほぼすべて網羅していたからです。今回は、実際に展覧会を体験した私が、特に印象に残った作品を基に、ピカソ作品の特徴について感じたことを書きたいと思います。
この記事を読めば、ピカソの絵がなぜ心を動かすのかが分かります。絵画鑑賞に興味ある人なら必ずどこかで出会うピカソを楽しめるようになると思います。
結論から言うと、ピカソの絵のエッセンスは以下の通りです。
- 一つの絵でたくさんの面を見せている
- どんなスタイルの絵でも上手く描ける
- ありがちなもの以外で何かを表現している
- それでも現実の上に立っている
- 有機的に画面を組み立てるために、形の変形がされている
特に鑑賞をおすすめする展示作品はこちら。順番に説明していきます。
展覧会の感想とピカソの絵が心に届く理由について

パブロ・ピカソ《丘の上の集落(オルタ・デ・エブロ)1909年(ベルクグリューン美術館蔵)》
集落と山々の風景画。風景を単純化し、幾何学で出てくる図形の集まりのように描かれています。無機的で、色合いも地味です。
それでもこの絵に目が留まるのは、家屋の視点がバラバラだからです。この家は正面の形が綺麗なので前から見た姿を描こう。この家は屋根のフォルムが格好良いので上から描こう。この家は意外と奥行きがあるのでこの角度から表現しよう、といった具合に、一つの絵で多くの視点を教えてくれます。
何も一つの視点だけを示す決まりはなかったのです。後にこの手法は、《緑色のマニキュアをつけたドラ・マール》など、女性の顔を描く際にも用いられています。きっと、自分が知っている色々な美しさを画面に描きたかったのでしょう。
一つの作品でたくさんの面を見せる。まるでピカソの画業そのものを表しているようです。
この作品は、ピカソがキュビズムを開始した最初期の作品です。ピカソはこの後、モチーフをさらに解体して形を作る「分析的キュビズム」、絵に現物を貼り付ける「総合的キュビズム」へと展開していきます。
《ポスターのある静物》(1912年. 国立国際美術館蔵)は、その二つの時代の特徴が表れている興味深い作品です。本展ではこのほか、画面に紙や木屑などを貼り付けた(パピエ・コレ)、総合的キュビズム期にあたる作品も展示されています。第2章にはキュビズムの作品が充実しているので、お時間がある方はじっくり観察してみてください。
パブロ・ピカソ《座って足を拭く裸婦》1921年(同蔵)
裸婦像。肌の光と陰やタッチから、ルノワールを感じさせます。豊満な裸体もルノワール風です。ピカソはどんな絵でも描けることが分かる一例です。
キュビズムでは、モチーフを解体して単純化していましたが、今度は逆に肉付けをして豊かさが復活しています。手足はルノワールよりむしろボリュームがあり、ふくよかな画風のボテロにも影響を与えていそうなほどです。
マンネリを感じたり、環境が変わったりすると、スタイルを思い切って変える勇気がピカソにはあります。
パブロ・ピカソ《大きな横たわる裸婦》1942年(同蔵)
横たわる裸婦。西洋絵画における伝統的な主題です。しかし、肌の色は鈍く、女性ならではの美しさが感じられません。
それどころか、体は岩のようにゴツゴツとしていて、生気すらもありません。
目を閉じて眠っていますが、身をよじらせて、苦痛にうなされているようです。こぶしを握りしめて、緊張が続いています。
制作は戦時中で、この絵が戦争を描いていることは確かです。絵の中に血は流れていませんが、そこに戦争が存在することが凄いのです。
定番モチーフで別のテーマを表現する。あるいは、あるテーマをありきたりなモチーフ以外で表現する。だから心に届くのです。
パウル・クレー《封印された女》1930年(同蔵)
クレーの女性像。黄土色の下地の上に、線が白い人物像を形作っています。
その線の流れはメロディーのようです。線が集まった口先には、何かを強調するように、あるいは象徴するように、大きな赤い点が施されています。口紅のようであり、留め具のようなもので口封じをされている姿にも見えます。
その上から顔全体を、黒い擦れ汚れがリズミカルに覆っています。全ての要素が調和して、女性の表情は困っているように映ります。
ピカソと同時代を生きたクレーもまた、誰も見たことのないような女性像を描きました。ピカソとの違いは、クレーの女性は空想上、いわば夢の世界を生きていることです。ピカソの女性は、あくまで現実から再現されています。モデルがいるのです。
アンリ・マティス《ニースのアトリエ》1929年(同蔵)
マティスの室内画。大きな窓がまず目に飛び込んできます。外には青い空と大きな雲、広い海が見えて開放的です。窓の下部分は何でしょうか。砂浜かテラスか、単純化されすぎていて判別できません。
いずれにせよ、絵の色は、この部分と天井とカーペットの薄い黄色が基調になっています。左側のカーテンも黄色です。
室内には、一番手前の肘掛け椅子をはじめ、椅子が何個も存在します。左側には、窓に向かって座り、作業をしている人物がいます。私もこの空間の椅子に座って時間を過ごしたい。
それほど、画面の色彩からは室内空間の快適な雰囲気が伝わります。逆に言えば、快適な心地を表現するために、色を選択しているのです。
心の動きを表現するために色を選び、その効果を高めるための関係性から、色をつけて成形するのがマティスの手法です。よく考えると、雲の位置が不自然な気がしますが、マティスの感覚ではこれが正解なのです。
ここで、同じく室内を描いたピカソの《窓辺の静物、サン=ラファエル》(1919年. ベルクグリューン美術館蔵、第3章にて展示)と比べてみましょう。
モチーフを単純化している点は同じですが、それは、画面を有機的に再構成するためであって、色を引き立てることが第一ではありません。ピカソとマティスは考え方が全く違う画家なのです。
今回の紹介は以上になります。
いつもご覧いただきありがとうございます!
よろしければTwitterのいいね・フォローをお願い致します。
[参考文献]
早坂優子(2006).『鑑賞のための西洋美術史入門 (リトルキュレーターシリーズ) 』.視覚デザイン研究所








コメント