芸術を見て、心豊かになろう!
今回、振り返る展覧会はこちら。
「パリ・オペラ座−響き合う芸術の殿堂」
2022年11月から東京・アーティゾン美術館にて開催された展覧会です。
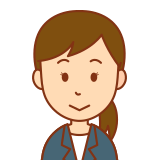
「オペラ座が”芸術の殿堂”って、つまりどういうこと?」
結論から言うと、オペラ座は、演者だけでなくあらゆる芸術家に活躍の舞台を与えてきたということです。
そこからまた新たな魅力が生まれるのです。
具体的に、そのことを実感した展示作品を振り返ってみましょう。
フランソワ・ブーシェ《優雅な羊飼い》1738年(フランス国立公文書館蔵)
上流階級の男女が戯れています。
ロココ時代の定番の題材ですが、本展で着目すべきは服装です。
男が着ているのは、オペラの衣装なのだそう。
ブーシェは、実は絵画だけでなく、衣装デザインやオペラの舞台装飾の分野でも活躍した画家でした。
同じくロココを代表する画家ジャン=アントワーヌ・ヴァトーによる雅宴画、《見晴らし》(1715年頃.ボストン美術館蔵)においても、男性がオペラ風の衣装や帽子を身につけています。
描かれているのは、森で歌い、愛を語らう貴族の男女の集いですが、現実のようでいて舞台の光景のようでもあります。
これらの作品から、18世紀ロココ時代におけるオペラと絵画の距離の近さが窺えます。
ロココ絵画の新しい見方が加わりました。
エドガー・ドガ《バレエの授業》1873-1876年(オルセー美術館蔵)
踊り子たちの稽古場の光景です。
つまりオペラ座の舞台裏ですね。
構図が斬新だと斬新だと思いませんか?
画面に踊り子たちが沢山入るアングルです。
そして、踊り子たちの様々な仕草や表情が描き分けられています。
ドガは、演者の素顔を覗くことに強い関心があったようです。
そのことは、《舞台袖の3人の踊り子》(1880-1885年頃.国立西洋美術館蔵)などの絵からも窺えます。
人には「舞台裏を知りたい」という欲望がある。
今の時代も舞台裏を伝える映像などは人気があるので、それは現代の人も同じなのでしょうね。
エドゥアール・マネ《オペラ座の仮面舞踏会》1873年(ワシントン、ナショナルギャラリー蔵)
オペラ座のロビーで開かれていたダンスパーティーの光景です。
男性は、シルクハットにタキシード姿ですが、仮面舞踏会という割にはほとんどが仮面を付けていません。
男性の数が多く、踊っている様子もあまり見られず、視線は数少ない女性に集まっています。
男たちの快楽が赤裸々に描かれているように映ります。
群衆の熱気という意味では、現代日本の渋谷ハロウィンのそれとそっくりです。
同じような光景は、《オペラ座の仮装舞踏会》(1873年.石橋財団アーティゾン美術館蔵)にも描かれています。
マネが徹底的に描き取ったのは、同時代の都会人の生活です。
革新的な主題でサロンの権威に受け入れられなかったマネですが、後世に名を残したのは受賞者よりも落選者のマネの方でした。
マルク・シャガール《ガルニエ宮の天井画のための最終習作》1963年(パリ、ポンピドゥセンター蔵)
オペラ座観客席の天井画(習作)です。
甘い色がモチーフごとに使い分けられていて、色彩豊かで優美な感じを与えます。
元はアカデミックな天井画だったのを、モダンにイメージ刷新する為に、シャガールに依頼が舞い込んだのだそう。
モチーフには、代表的な音楽家とそれぞれの演目がシャガール流に描かれています。
オペラに疎い私は、チャイコフスキー《白鳥の湖》くらいしか分かりませんでした。
気になって後で調べてみると、以下の14の作曲家と作品でした。
- ラヴェル バレエ「ダフニスとクロエ」
- ドビュッシー/オペラ「ペレアスとメリザンドに」
- ラモー/作品不明
- ベルリオーズ/劇的交響曲「ロメオとジュリエット」
- ワーグナー/楽劇「トリスタンとイゾルデ」
- モーツァルト/オペラ「魔笛」
- ムソルグスキー/オペラ「ボリス・ゴドゥノフ」
- アダン/バレエ「ジゼル」
- チャイコフスキー/バレエ「白鳥の湖」
- ストラヴィンスキー/バレエ「火の鳥」
- ベートーヴェン/オペラ「フィデリオ」
- ヴェルディ/オペラ「ラ・トラヴィアータ(椿姫)」
- ビゼー/オペラ「カルメン」
- グルック/オペラ「オルフェオとエウリディーチェ」
一つひとつが夢の世界で、順に見ていくと、まるでパレードを眺めているような素敵な気持ちになります。
オペラへの愛とリスペクトが詰まっていると思います。
お披露目時の、オペラを愛する人々の満足気な顔が目に浮かびました。
ジョルジョ・デ・キリコ《『バッカスとアリアーヌ』バッカスの衣装デザイン》1931年頃(フランス国立図書館蔵)
全身オレンジ色模様の衣装デザインです。
腹、肘、膝に太陽のようなマークと、そこから波線が放射状に伸びていて、かなり奇抜な感じを与えます。
これが神の衣装というのだから驚きます。
流石に気付かれないと思ったのでしょうか、「私が神だ」と言っているようなポーズをしています。
暖色の波線なので、中心から何かエネルギーが湧き、力がみなぎっているようです。
黒いロングコートかマントのようなものを抱えているので、普段は正体を隠しているのかもしれません。
いずれにせよ、斬新な舞台衣装で、内容が気になります。
デ・キリコは形而上絵画の画家で、後のシュルレアリスムに強い影響を与えました。
他にも前衛的な画家が、20世紀になると舞台美術やポスターなど制作に関与しています。
例えば、
モーリス・ドニ、ピエール・ボナール:ナビ派
アンリ・マティス、アンドレ・ドラン:フォーヴィズム
フェルナン・レジェ:エコール・ド・パリ
アンドレ・マッソン:シュルレアリスム
ヴィクトル・ヴァルザリ:オプアート
などです。
伝統は、時代に合わせて革新し続けることで守られる。
そんなことをパリ・オペラ座は教えてくれます。
パリ・オペラ座が人々を魅了し続ける秘密もここにありそうです。
以上になります!
最後まで読んでいただきありがとうございました!
Twitterのいいね・フォローよろしくお願いします!
[参考文献]
早坂優子(2006).『鑑賞のための西洋美術史入門 (リトルキュレーターシリーズ) 』.視覚デザイン研究所






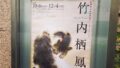

コメント