「かえる観覧帳」を読みに来てくださり有難うございます。
今回紹介する美術館はこちら!
大原美術館(岡山・倉敷)
倉敷の実業家が設立した日本初の西洋美術館です。美観地区にある建物に、画家と蒐集家の思いが今も残っています。
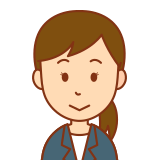
大原美術館の見どころを知りたい
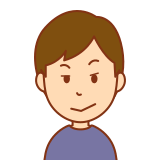
入館料2000円は常設展としてはやや高めだけど、それでも見る価値はあるの?
こんな人のための記事です。
結論から言うと、大原美術館の常設展は見る価値が十二分にあります。なぜなら、西洋絵画コレクションの質は日本屈指だからです。国内外の企画展へ貸し出される作品が多いです。
具体的に何を見たらいいの?そんな方のために、実際に行ってみて魅力を感じた大原美術館コレクションの作品を7つ厳選してご紹介します。
あくまで私が個人的に気になった作品なので、感想が違うところもあると思いますが、楽しんで読んでもらえたらと思います。
この記事を読むことで、大原美術館の見どころを知り、皆様の日常と美術館の距離を近づける一助となれば嬉しいです。
早速ですが、今回私が選んだ作品はこちらです。
順番に解説していきます。
「大原美術館」常設展の絶対に見る価値ある作品7選

エル・グレコ《受胎告知》1590-1603年頃
大原美術館の看板であり、その表現が歌劇のクライマックスシーンように劇的で新しい作品。
16世紀末に制作されたエル・グレコの《受胎告知》は、日本で見られる宗教画の古典として珍重されています。
主役のマリアとガブリエルの衣服には、原色の赤と黄が鮮やかに使われ、幸福感が溢れています。伸びたように描かれた腕や指が、いかにもエル・グレコらしい特徴。体をねじった対角線の構図や、暗闇と光の対比が醸し出す雰囲気がドラマチックです。
この絵には人々を魅了する要素が詰まっています。
クロード・モネ《睡蓮》1906年
日本のためにモネが選んだ《睡蓮》。光と色彩の織りなすドラマが、大原美術館を彩っています。
描いたのは昼下がりの時間でしょうか。太陽は高く、蓮の葉が鮮やかな緑に輝いています。その明るさは、黄色い花たちに負けていません。
池の表面には、空と雲と柳の枝が風に揺れる様子が映っています。水中の水草がゆらゆらと泳いでいます。
モネの《睡蓮》は、その美しさを画面の外の広い空間にまで感じさせ、心を打つ作品です。
ブリジット・ライリー《花の精》1976年
この絵、動いてる?
ブリジット・ライリーによる《花の精》の絵画は、見続けると画面がうねり出すように感じられて面白い。
曲線と色彩のパターンが錯覚を引き起こしていて、視覚的な体験を与えてくれるオプティカル・アート(オプ・アート)の特徴をよく示しています。
画家は、どう表現するかよりも、人の目にどう見えるかを追求しているようです。誰もが同じ受け取り方をすることは難しいけれど、それを目指すとするとこうした人間の特性に基づいた作品に行き着くのかもしれません。
ジャクソン・ポロック《カット・アウト》1948年-58年
これもアートなの?
ポロックの《カット・アウト》は、絵の具を垂らしたカンヴァスの中央を大胆に切り抜いた絵画。
カンヴァスを床に置き、絵の具を垂らす手法(ドリッピング)が用いられ、偶然な絵の具の線や丸点が、何かをイメージすることの束縛から解放してくれます。
一方、ナイフで切り抜かれた形は、均質で上下左右のない画面も相まって、色々なものに見立てることができ、想像力をかき立ててくれます。
絵を描くという作家の身体的な行為そのものが画面に表現された芸術(アクション・ペインティング)で、どのようにして完成したのだろう?とそのプロセスを想像すると面白い。
アートの概念について、全く新しい考えを教えてくれます。
アメデオ・モディリアーニ《ジャンヌ・エビュテルヌの肖像》1919年
大原美術館にあるモディリアーニの絵画《ジャンヌ・エビュテルヌの肖像》に描かれているのは、画家の恋人。
黄色いセーターを着た彼女のお腹あたりを見ると、子どもを授かっているのかもしれません。
モディリアーニ作品で鑑賞すべきポイントの一つは、目の表現。白目だったり、デフォルメされて抽象的でありながら、かえって心理面をよく表しています。
この絵も、なんだか幸せそうな感じがしてきませんか。
安井曾太郎《外房風景》1931年
大原美術館は日本洋画も素敵。安井曾太郎の絵画《外房風景》は、房総の海岸と民家を見渡すパノラマの風景画です。
山の塗り方や、日本家屋の構築的な連なりに、どことなくセザンヌの影響を感じます。そうした西洋の影響を受けつつも、近景に映り込む松の木、当時の空気を感じさせる波の動き、何より色調の落ち着いた明るさが、侘び寂びを感じさせます。
単なる西洋からの輸入ではない、日本人の心に馴染む油彩の風景画です。
ポール・ゴーギャン《かぐわしき大地》1892年
大原美術館には、世界中の美術館から注目されるゴーギャン作品があります。南国の大地に立つ裸婦の絵。
地面や木の幹の色は、はっきりとした輪郭で平たく塗り分けられています。そしてその色味が独特です。異国のエネルギーを感じます。
女性は旧約聖書に登場するイヴをモデルにしていて、西洋のキリスト教美術とタヒチの原始的な民族美術が共存しているのが面白い。
リンゴの代わりに固有種らしき花、ヘビのかわりに赤い羽の怪鳥が描かれ、タヒチを楽園とみなしていて、ゴーギャンがタヒチへ赴いた理由がうかがえます。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
みなさまもぜひ大原美術館で自分のお気に入りの絵を見つけてください。
どの絵に惹かれるかは、もちろん人によって異なります。何に心を動かされたかを知ることは、自分自身の状態や価値観を知ることにもつながります。お気に入りの絵を見つけることで、あなたの日常をより豊かにしてもらえたらと思います。
このブログでは、ミュージアムや展覧会のさまざまな活用法をお届けしています。
Instagramもやっています。有意義な情報、有益な情報を投稿していきますので、ぜひフォローをお願いします。
Instagram →tasuku(@tasukuasi.museum)
あなたの目に映る日常風景に「美」が届きますように!
ではまた!








コメント