ミュージアムへ行って、心と頭を動かそう!本日の展覧会はこちら!
国立国際美術館 コレクション展
国立国際美術館は、大阪・中之島にある国立の美術館で、国内外の現代アートを幅広く紹介しています。
ちなみに、近隣にも近現代美術を扱う大阪中之島美術館があります。大阪中之島美術館と国立近代美術館の違いは、大阪中之島美術館が、佐伯祐三をはじめとする、大阪と関わりのある近現代の美術作品に特色があるのに対し、国立国際美術館はより現代、より広い国内外のアート動向を扱っていることです。
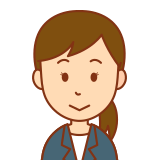
常設の「コレクション展」の見どころが分からない……
企画展などで国立国際美術館を訪れた際、常設コレクション展の見どころが分からず、素通りしてしまう方もいらっしゃるでしょう。特に、現代アートを難しく感じている方は尚更だと思います。
そこで今回は、美術館を実際に見学した私の体験を基に、国立国際美術館の魅力が詰まったコレクションを5点ピックアップして解説します。
この記事を読めば、国立国際美術館の見どころが分かるので、コレクション展をより楽しむことができます。
展示替えの関係で、今回紹介する作品を一度に見ることはできないかもしれませんが、魅力の本質を掴むことができれば、コレクション展の楽しみ方の参考にしていただけると思います。
結論から言うと、国立国際美術館の見どころは、実践で思考力を身につけることができる現代アートのコレクションです。確かに現代アートは難しいです。鑑賞に答えがありません。だからこそ考える力が求められます。そして、国立国際美術館は優れた現代アートが揃う全国有数の美術館で、楽しく頭を動かすのに絶好の場所だと思います。
具体的な作品ラインナップはこちら!順番に紹介します。
思考力を身につけるおすすめ展示物5選

ジョアン・ミロ《無垢の笑い》1969年(国立国際美術館蔵)
館内の壁にあるひときわ大きな作品。タイトルからかけ離れたイメージにまず戸惑います。
640枚の巨大な陶板画の中に、たくさんの目が描かれています。目の色は、赤・黄・青・緑とさまざまな原色です。タイトルの「無垢」とは、他の色と混じっていないことを指しているのでしょうか。
では、「笑い」はどうでしょう。どこをどう見ても笑っていない目です。これは笑いなのでしょうか。笑いというのは、他との交わりの中で生まれるものです。他者との交流のない「無垢な笑い」など存在しないことを示唆しているように思いました。
高松次郎《ネットの弛み》1969年(同蔵)
格子状に張られたロープが弛んでいます。視認の確かさについて考えさせられます。
しかし、よく見ると弛んでいるのは内側だけで、外側はピンと張られており、外と内で長さが違っていることが分かります。
したがってこの弛みは、自然にできたものではなく、意図的に作られた(計算された)ものです。つまり、最初に抱く認識は偽りで、実際の事実と異なっていることになります。
同様のことを、高松次郎は《影》という作品でも表現しています。こちらは国立国際美術館に常設してあるので、是非探してみてください。自分の目がいつでも正しいわけではないことを戒めてくれる作品です。
荒川修作《言葉のような線》1963年(同蔵)
カンバスに油彩という絵画の伝統様式で描かれた、図形のような絵。これもアートなのでしょうか。
画面中央にあるのは、家の平面図のようです。その両端に切れかかっている「Living Room」の文字。その文字から中央に向かって何本もの矢印が引かれています。
これを「言葉」とするならば、居間で交わされている2人の会話を表した絵といえます。立体的な現実を平面的なカンバスの中に表現するという意味では、これも伝統的な絵画です。
ここから、どのような会話がなされているかイメージを立ち上げることができます。「アートの本質は思考そのものにある」という考え方を体現したような作品です。
思考や感情を引き出すことができれば、それはアートです。本質を捉えていれば、形式に縛られなくていいのです。別の表現を考えてみましょう。
河原温《JUNE 23, 1980, Todayシリーズ(1966-2013より)》1980年(同蔵)
日付だけが描かれた絵。単に日付を描いているのではなく、「いま自分が何者であるか」ということを描いています。
黒の単色で塗られた背景に、白で年月日だけが描かれています。
これを見て何を考えますか?画家がこの制作に至った1980年6月23日の出来事?この日にあった社会の出来事?あるいは、この日に自分が何をしていたか?
その隣には、内側にその日の新聞が納められた、ボール紙の箱が展示されています(もちろんこれも作品です)。
河原温は、制作した日付を描くこの日付絵画シリーズを、ルーティンのように独自のルールに従って制作し続けたそうです。
また彼は、公の場に姿を現すことはせず、作品発表によってのみ自分の存在を知らせました。あくまで芸術家として存在し続けることを貫いたのです。
今日、自分が残せることは何でしょうか。
ヘンリー・ムーア《ナイフ・エッジ》1961/76年(同蔵)
人体を模したようにも見える彫刻。印象における頑丈さと重さの関係性を切り離しています。
正面から見ると、どっしりと存在感のある物体。横から見ると実は、刃物の先端のように薄く、その印象はあっという間に崩れます。
この作品もまた、私たちの認識がいかに不正確で脆弱かを教えてくれます。判断材料となる情報を一つに頼ると危険だということがいえるでしょう。
今回の紹介は以上です。
思考力を伸ばしたい人には、こちらの本もおすすめです。この本で思考方法を学んでから、美術館で実践してみるのも効果的です。
「答えのないゲーム」を楽しむ 思考技術 高松 智史 (著)
最後までお読みいただきありがとうございます。
もしよろしければ、Instagramのフォローをお願い致します。







コメント