芸術に触れて、心を動かそう!本日のテーマはこちら!
「風景の見かた」
- 風景を見る感覚を研(みが)きたい
- 風景写真を上手に撮りたい
そんな方にオススメなのが、先日私が見学した長野県立美術館の「東山魁夷館コレクション展」です。
日本を代表する風景画家である東山魁夷。画家が愛した空気の中で、東山魁夷と出会える美術館です。
東山魁夷は、「風景は心の鏡である」という言葉を残しました。実際に彼は、風景の中に深奥な精神世界を具現化しています。
今回の記事では、東山魁夷館を見学してきた私の体験を基に、風景鑑賞をより楽しむためのヒントになりそうなことについて書きたいと思います。
この記事を読めば、一流の風景画家が何に感動し、何を表現しようとしたかが分かるので、風景とのより深い向き合い方や、せンスの良い風景写真の撮り方の参考になります。
具体的な作品ラインアップはこちら!順番に解説します。
東山魁夷館コレクション展で知る風景の見方

《霧氷の譜》1985年(長野県立美術館蔵)
樹形に沿って付いた氷。風景に奥行きがあります。
一本の幹から枝が連綿と分かれていて、繋いできた生命の長さを物語っています。幹の奥にもある見えない枝を想像すると、果てしない奥行きを感じます。
静かでキーンと張り詰めた空気。全ての音が奥深くへ吸い込まれそうです。無音の世界が表現されています。
《松と月》1973-85年(同蔵)
松林から見上げる満月。鑑賞者の感情の動きが反映されています。
月の光が暗闇にぼんやりと広がっています。ピントが合っておらず光が動いているようにさえ感じます。
木の葉の輪郭が曖昧で、月光に影響を受けているようです。絵肌はやはり全体的にぼんやりとしていて、考え事に耽っている時に目に映る景色と似ています。
感情によって風景の形が揺れている様子は、ゴッホの《星月夜》を思わせます。
《倉庫》1963年(同蔵)
レンガ造りの倉庫の壁面。平面に人間社会の記憶が深く刻まれていて、重厚感があります。
レンガの色がまだらで、汚れやはげているのが分かります。窓がたくさんありますが、この壁の奥に何があるのでしょうか。想像をかき立てられます。
人々の営みの時間が重層的に保管されているような作品です。
《静晨》1994年(同蔵)
冬山の朝ぼらけ。画家が感動する冬の時間帯が表現されています。
画面には至って静かな時間が流れています。薄暗い白を基調とした画面の中で、点在する針葉樹の黒色が強調されていて、画家の目に印象的に映ったのかもしれません。
少しずつ色が浮かび上がる時間が切り取られていて、この静寂な時間を愛してやまない画家のまなざしが感じられます。
《冬の旅》1989年(同蔵)
雪が深く積もった山。どことなく懐かしさを誘う日本の原風景が描かれています。
木立が山の稜線に水平に並んで、リズミカルです。まるで音楽を奏でているみたいです。画面の色は穏やかな暖色系の白色です。暮れなずむ時間帯の茜色といいましょうか。この絶妙な色合いが、古くから慣れ親しんだ感じを与えていると思います。
東山魁夷の絵を見ると、白にもさまざまな種類の色があることが分かりますね。
今回の紹介は以上です!
東山魁夷館では季節ごとに展示替えを行なっていて、いつ訪ねてもその季節に合わせた素晴らしい風景画を鑑賞することができます。ぜひ足を運んでみてください。
東山魁夷に興味がある方には、こちらのエッセイ本もおすすめです。
「風景との対話 (新潮書)」東山 魁夷 (著)
最後までお読みいただきありがとうございます。
もしよろしければ、Instagramのフォローをお願い致します。





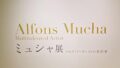

コメント