今日も「かえる観覧帳」を読みに来てくださり有難うございます。
今回行ってきた展覧会はこちらです!
森美術館開館20周年記念展『ワールド・クラスルーム:現代アートの国語・算数・理科・社会』
2023年4月から森美術館(東京・六本木)にて開催されました。学校の教科を現代アートで学ぶ展覧会です。
教科書としてのアートが、考える力を磨く格好の教材になっています。他の分野へ、知らなかった世界へ連れ出してくれる作品も多く、思考の旅を楽しめます。
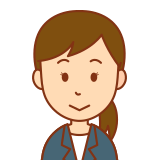
現代アートの楽しみ方を教えてほしい!
そんな方のために、この記事では、実際に展覧会に行ってみて楽しめたアート作品を5つ選んで紹介します。
あくまで私が個人的に気になった作品なので、感想が違うところもあると思いますが、楽しんで読んでもらえたらと思います。
この記事を読むことで、現代アートの楽しさを知り、あなたの美術鑑賞を充実させる一助となれば嬉しいです。
早速ですが、今回私が選んだ作品はこちらです。順番に解説していきます。
企画展「ワールド・クラスルーム」(森美術館)の面白いアート5選

【国語】ジョセフ・コスース《1つと3つのシャベル》1965年(滋賀県立美術館蔵)
なぜ人に伝わらないのか。それは、どんな表現も自分の認識を完全に伝えられないから。
ジョセフ・コスース氏による《1つと3つのシャベル》のアートは、実物のシャベルと、シャベルの写真と、辞書に書かれたシャベルの定義を並べています。3つとも異なる表現方法だけど、どれもシャベル。
しかしながら、それぞれから認識するものに微妙に違いがあります。
誰がやっても認識のズレが生じて当たり前。生じたズレを知り、埋めていく作業の方が大事ですよね。
【社会】森村泰昌《肖像(双子)》1989年/《モデルヌ・オランピア2018》2017-2018年(森美術館蔵)
自分がやっていいか悩むのはムダ。なぜなら、自分ではダメな理由なんて大して無いから。
森村泰昌氏による《肖像(双子)》と《モデルヌ・オランピア2018》のアートは、マネの名画《オランピア》の中に画家自らが入り込んでいます。西洋画の裸体モデルが白人でなければならない理由など無かったのです。
絵画のモデルに人種や性別は関係ありません。
自分がやってはいけない理由に不必要に縛られていませんか?
【哲学】李禹煥(リウファン)《関係項》1968/2019年(森美術館蔵)
自分を変えられないなら、場所を変えるという選択。
李禹煥氏による《関係項》のアートは、重ねられた鉄板とガラス板の上に大きな石を置いています。ともに素材そのままですが、自然では出会わない組み合わせです。非日常の関係性が、空間を面白くしています。
無理して自分を作らなくていい。あるがままの自分で、自分が絶対に行かない場所に行ってみてはどうだろうか。何が起きるか見てみよう。
【算数】杉本博司《楕円面を覆う一般化されたヘリコイド曲面》2023年(作家蔵)
ビジネスのアイデアは、外側の世界からも発見できるものです。
杉本博司氏による《楕円面を覆う一般化されたヘリコイド曲面》のアート作品は、数理モデルをアルミニウムで実際に再現しています。
つまり、数学的な規則性からは想像もつかない美を見出し、芸術の中に見事に引き出しています。
モチベーションが下がった時、別の世界で興味を追求することで新しい視点が開けるかもしれません。
【理科】宮永愛子《Root of Steps》2023年(作家蔵)
移り変わることを恐れてはいませんか。
宮永愛子氏の《Root of Steps》というアート作品は、常温で昇華するナフタレンという素材を使用して靴を制作しています。そのため、展示期間中に靴の形は徐々に変わり崩れていきますが、再結晶によって物質は展示ケース内のどこかに存在し続けます。
形は変われど、そこにある。
物事は移り変わりますが、その本質は消えることなく、確かに存在しています。そう思うと安心できませんか。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
現代アートは、楽しく「考える力」を磨く魅力的な手段です。作品の解釈や背後にあるコンセプトを考えることで、創造性や批評的思考が育まれ、自分の視点を深める喜びを提供してくれます。
みなさまもぜひ現代アートに会いに行ってください。
このブログでは、ミュージアムや展覧会のさまざまな活用法をお届けしています。
Instagramもやっています。有意義な情報、有益な情報を投稿していきますので、ぜひフォローをお願いします。
Instagram →tasuku(@tasukuasi.museum)
アートで心を動かして、人生を豊かにしよう!
ではまた!








コメント