美術館へ行って、心の豊かさを得よう!
本日の展覧会はこちら。
京都国立近代美術館(MoMAK)常設展「コレクション展」
4階コレクション・ギャラリーにて、年5回の展示替えを行いながら開かれている所蔵作品展です。
その特徴は、京都画壇から西日本に関わる優れた美術作品を、所要時間30分ほどでさくっと鑑賞できること。
タイパ(タイムパフォーマンス)が高いという点で、個人的におすすめの展覧会です。
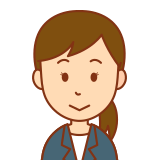
MoMAKコレクション展の見どころが分からない・・・
そんな方のために、
最近の展示作品の中から、是非見ておきたいMoMAKコレクションの代表作を5点ピックアップして解説します。
展示替えの関係で、今回紹介する作品を一度に見ることはできませんが、
同作家の他作品(それもまた素晴らしい)が展示されているケースも多いので、
コレクション展の見どころや楽しみ方の参考にしてもらえると思います。
それではさっそく紹介していきます。
コレクション展で見ておきたい展示品を紹介
土田麦僊《大原女》昭和2年(京都国立近代美術館蔵)
草上で休息する3人の大原女。
独特のおしゃれな仕事服が絵に映えます。
薪や柴が無いことから、売り終えて京の町から帰ってきたところでしょうか。
足を撫でていて、少し歩き疲れた様子です。
木立の奥に見える里が大原だと思われます。よく見ると薪らしき木材が積まれていますね。
たんぽぽが咲く陽春の候。
束の間の時間の穏やかさや働く女性の美しさはいつの時代も同じようで、共感を覚えます。
ちなみに京都国立近代美術館には、土田麦僊の初期の代表作である《海女》(大正2年)も収蔵されていて、こちらも一見の価値があります。
麦僊の初期の特徴である、ゴーギャンの影響が見られる作品です。
福田平八郎《緋鯉》昭和5年(同)
5匹の鯉が泳いでいます。
蝋燭の火のように赤い4匹と神秘的なまでに白い1匹。
鱗の洗練された写実が、作品の趣に結び付いているように思います。
よく見ると水面に波紋が。見上げると雨が降っています。
それも気に留めない様子で、優雅に泳ぐ鯉たち。
あちらの世界には閑寂な時間が流れているようです。
福田平八郎は、後にモダンな日本画を展開していくようになります。
上村松園《虹を見る》昭和7年(同)
母子と若い女性が見ているのは虹。
母親は赤ん坊の関心に寄り添っていて、その愛情に微笑ましくなります。
一方、若い女性が手に持つ団扇は山水の絵柄で、自然の美しさを愛する人なのでしょう。
表情の慎ましさ、手先の所作の淑やかさ、着物の裾にかけての流線など、上村松園が描く美人画はどこを見ても気品に満ちています。
装束の文様や髪飾りの装飾の見どころもやはり健在です。
西村五雲《吉野の桜》明治中期(同)
山道の崖側に沿って咲き連なる桜。壮観です。
蕾の濃い色が見えるので、まだ五分咲きといったところでしょうか。これから見頃を迎えそうです。
花の輪郭が横に広がっていて、風の存在が感じられます。
霧が発生する早朝の風景でしょうか。
まだ肌寒い春の朝に、崖っぷちで踏ん張って花を咲かせる桜の木々の、生命の力強さに感動を覚えます。
西村五雲もまた京都画壇に属し、竹内栖鳳の弟子に当たります。
山種美術館(東京)には五雲の出世作である《白熊》(明治40年)が収蔵されているので、関東にお住まいの方は是非ご覧になってください。
小出楢重《裸女結髪》昭和2年(同) ※新収蔵
背を向けて腰を掛け、鏡を見ながら髪を結う裸女。
くびれの細さがデフォルメされて強調された所から、独自の女性像表現を追求する画家の意志が感じられます。
肌の色は暖色系で、しっとりとした質感で、西洋人よりは日本人に近い肌が表現されています。
これらの特徴により、独特の日本近代的な絵画世界が作り出されています。
作者の小出楢重は、岸田劉生や萬鉄五郎、中村彝らと同時代で、大阪モダン文化を象徴する洋画家です。
京都国立近代美術館の所蔵にふさわしい一品だと思いました。
京都国立近代美術館でランチ・カフェ

1階に「カフェ ド ゴマルゴ(cafe de 505)」があります。
今回は、ランチにゆばカレーを食べました。
ゆばがとろとろでおいしかったです。
今回の紹介は以上です。
最後まで読んでいただきありがとうございました!
Twitterのいいね・フォローよろしくお願いします!
[参考文献]
辻惟雄(2021).『日本美術の歴史 補訂版』.東京大学出版会








コメント