アートを見て心を動かそう!本日の展覧会はこちら!
「甲斐荘楠音の全貌ー絵画、演劇、映画を越境する個性」
2023年2月から京都国立近代美術館(京都・岡崎公園内)にて開催された展覧会です(東京ステーションギャラリーへ巡回予定)。京都画壇の個性派、甲斐荘楠音の多面性に光を当てています。
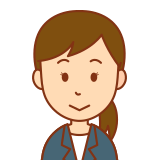
展覧会の感想は?甲斐荘楠音ってどんな画家?
そもそも、「甲斐荘楠音」の読み方が分からない方もいらっしゃるのではないでしょうか。(「かいのしょうただおと」と読みます。)あやしい日本画を描いたことで近年人気が高まっているユニークな日本画家です。
今回は、「甲斐荘楠音の全貌」展に行ってきた私の体験を基に、甲斐荘楠音の魅力が分かるおすすめの作品をご紹介します。
この記事を読むことで、あやしいだけじゃない甲斐荘の魅力が分かるので、京都画壇や日本画の新しい見方を得ることができます。
結論から言うと、この展覧会で分かったのは、甲斐荘の表現者としての執念が、絵画、演劇、映画分野の境界線を良い意味で退廃させていたことです。職業の領域というのは、自ら縛る必要はなく、もっと柔軟に考えていいのだと感じました。
具体的に、鑑賞をおすすめしたい甲斐荘作品はこちらです。順番に説明します。
甲斐荘楠音の魅力が分かる作品を紹介
《畜生塚》1915年頃(京都国立近代美術館蔵)
嘆き悲しむ女性の裸体群像。役者のように自ら場面を演じて、悲しみの感情を描いています。
日本人離れした手足の長さ。輪郭線ではなく、陰影の変化を駆使した立体表現に甲斐荘が若い頃に傾倒したレオナルド・ダ・ヴィンチからの影響が感じられます。
画面中央には、同じく関心があったミケランジェロの、バンディーニのピエタを参考にしたとされる構図が見られます。ピエタとは、キリスト教美術の聖母子像で、十字架から降ろされたイエスの亡骸を聖母マリアが抱えて嘆き悲しむ姿を扱ったものです。
女性の人体を筋肉質で力強く描いていることからも、ミケランジェロへの憧れを感じます。美人画を多く描いた甲斐荘の関心が、柔和なラファエロではなく、逞しいミケランジェロだったのは、個人的に興味深い事実です。
画面右側の、両手で顔を覆って悲しみに暮れる女性に注目してください。本作の近くに、同じポーズをとった甲斐荘の写真が展示されています。処刑されようとする状況の女性になりきって、強い悲しみを表現しようとする表現者としての姿勢に心を打たれます。
「場面を演じて描く」という点では、甲斐荘の舞台好きがうかがえる《道行》(1924年. 京都国立近代美術館蔵)も見どころです。
《虹のかけ橋(七妍)》1915-76年(京都国立近代美術館蔵)
遊女の美人群像。自ら扮して、着物姿の綺麗さを描いています。
7人の太夫(たゆう)が、競い合うように、色とりどりで豪華な衣装を纏って並んでいて、見惚れてしまいます。1枚の長い手紙が、太鼓橋をかけるように7人を繋いでいて、まるで風景を眺めているようです。
中央の女性は一際、顔が整って、表情も凛として、存在感があります。同様の姿に扮した甲斐荘の写真が近くに展示してあります。この女性にパワーを感じるのは、他者ではなく自己を描いているからかもしれません。
「衣装に扮して描く」という点では、《桂川の場へ》(1915年. 京都国立近代美術館蔵)も見逃せません。火鉢の前の女性の所作や表情が丹念に描かれています。
また、着物姿の綺麗さを描いた作品としては、ニューヨークのメトロポリタン美術館から《春》(1929年)が来日していて必見です。横たわる明るい着物姿の日本女性は、さぞかし海外の多くの人の目を喜ばせていることでしょう。
着物への造詣の深さから、後の甲斐荘は衣装考証として映画に携わるようになります。映像や宣伝ポスターへの映り方まで計算されたような衣装のデザインは見事です。まるで、映画の世界でも、画家として映像の「絵」を描いているようです。
《籐椅子に凭れる女》1931年頃(京都国立近代美術館蔵)
椅子に凭(もた)れる美人画。透けて見える「肌香(はだか)」を描いています。
視線を右に真っ直ぐ向けている目元は血色が悪く、不気味な感じを与えます。モデルが椅子に凭れるポーズは、それだけで充分に色気を表せています。しかし、白い肢体をあえて黒い生地から透けさせて描くことで、その艶かしさを存分に表現しています。
裸を「肌香」と言い表し、香りまで捉えようとした甲斐荘の表現者としてのこだわりが見える作品です。
《幻覚(踊る女)》1920年頃(京都国立近代美術館蔵)
舞姿の美人画。動きの一瞬を捉えて、なおかつ女の内面を演劇的に演出しています。
紅い着物の輪郭がぼやけていて、ゆらゆらと形を変え続ける炎の残像のようです。生で見ると分かるのですが、着物の表面にキラキラと輝く文様があり、火の粉が飛んでいるようにも見えます。
光が当たっている芸妓の背後には不気味な手の影が。見えないはずの、人を惑わす女の情念が象徴的に反映されています。照明演出的に描いている点に、現代演劇にも通じる要素があります。
《横櫛》1916年頃(京都国立近代美術館蔵)
小説の表紙(岩井志麻子の『ぼっけえ、きょうてえ』)にもなった、代表作の美人画。
女性を単に美しく描くのではなく、あやしく描いています。
目のまわりが暗く、病的な感じです。口元はうっすらと微笑みを浮かべていて、あやしい感じを強調しています。羽織りを着崩していて、退廃的な雰囲気が漂う美人です。着物の柄も異様で、激しく燃え上がる炎のような文様があり、不気味です。生で一度見たら忘れられないほど、強烈な個性を放つ美人画です。
今回の紹介は以上です。
最後までお読みいただきありがとうございます。
もしよろしければ、Twitterのいいね・フォローをお願い致します。
[おすすめ書籍]
青柳正規 監修(2023).『小学館の図鑑NEOアート 図解 はじめての絵画(小学館の図解NEOアート)』.小学館








コメント