ミュージアムへ行って、心と頭を動かそう!本日の展覧会はこちら!
国立科学博物館 常設展
国立科学博物館は東京・上野公園にある国立の博物館で、日本の自然と日本人の関わりをみる日本館と、生命の進化と科学の進歩をみる地球館で構成されています。
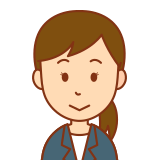
国立科学博物館の常設展には何があるの?
恐竜博、ミイラ展、深海展など、科学に関する興味深い特別展で注目を集める国立科学博物館ですが、常設展では何を見たらいいか分からない方もいるかもしれません。
そこで今回は、私が実際に国立科学博物館に行ってきた体験を基に、私が選んだおすすめの展示物6選を紹介します。
この記事を読めば、国立科学博物館の良いところが分かるので、特別展だけでなく常設展も楽しく時間を過ごすことができます。
結論から言うと、国立科学博物館の常設展示には、子どもだけでなく大人も関心を持って楽しめる展示物がたくさんあります。そのため、お子さんやお連れの方とお話をしながら、一緒に科学への興味や考える力を育むことができます。
今回紹介する展示物はこちら。順番に説明します。
子どもも大人も楽しめるおすすめ展示物6選

フタバスズキリュウ/日本館3F
極端に首が長い首長竜の全身骨格標本。日本館3F北の入り口で、首を長くして待っている”かはく”(国立科学博物館の略称)の顔です。
関節がいくつも連なっていて、首がくねくねと自在に曲がりそうです。胴はたまご型でころんとしています。手足(ヒレ)の先は指のように骨が枝分かれしているのですね。器用に動かせそうです。
フタバスズキリュウは、約8,000万年前の白亜紀後期に(ティラノサウルスとざっくり同期!)、日本近海で生息していました。全長は6メートル以上あります。
日本の海をこのような巨大生物が泳いでいたのですね。骨格標本には、その形から実際の体つきや暮らしを想像する楽しさがあります。
ニホンオオカミの剥製/地球館3F
むかし日本にいたオオカミの剥製。日本に現存するのは3体という絶滅種の貴重な剥製です。
”オオカミ”にイメージするようなどう猛さはなく、むしろ見た目は可愛い!しかし手足の爪は鋭く、やはり野生味はあります。その表情にはどこか切なさが。種の歴史や生物多様性を守ることの尊さを実感します。
地球館2Fの動物の剥製群のコレクション(ヨシモトコレクションを含む)は充実しているので、あなたの好きな動物の剥製を見つけられると思います。ちなみに、日本館2Fには忠犬ハチ公がいますよ!
「しんかい6500」1/2模型/地球館2F
「しんかい6500」は、海の中を深さ6,500メートルまで潜ることができる調査船です。その使命は主に次の通りです。
- 地球内部の動きをとらえて、地球の成り立ちを解明する
- 深海の生態を調べて、生命の進化を解明する
- 地球環境の変動の歴史を解明する
国立科学博物館には、その1/2サイズの模型が展示されています。3人の乗員が乗るコックピットは、球状で、スペースは必要最小限です。あとは、さまざま機能を持つ機械が、まるで生き物の内臓のように、有機的に配置されています。深海の過酷な環境に耐えるため(主に水圧との戦い)、日本の科学技術の粋が集まっています。
注目したいのは覗き窓です。その小さなすり鉢状の窓からは、きっと神秘的な世界が見えるのでしょう。国立科学博物館に展示されている、あの大きなダイオウイカに遭遇することもあるかもしれませんね。
宇宙線の観察(霧箱)/地球館B3F
宇宙には、宇宙線という高エネルギーの小さな粒子が飛び交っています。それはもちろん地球上にも、遠い宇宙から常時降り注いでいます。
目に見えない宇宙線を見るための道具が、霧箱(きりばこ)です。霧箱を眺めていると、流れ星を発見するように、光が現れます。宇宙線が霧箱を通り過ぎた跡です。宇宙を身近に感じることができます。
科学の実験や観察の面白さを体感できる展示です。
アーケロン(巨大ウミガメ)/地球館B2F
アーケロンは史上最大のウミガメです。全長は4メートル以上。アーケロンが生息したのも白亜紀後期(約7,500万年前)です。北アメリカの内海を泳ぎ回っていました。
国立科学博物館のアーケロンは、実にダイナミックで生命感に溢れる展示です。
頭上に体を傾けて展示されていて、見上げると、本当に巨大なウミガメがこの空間を泳ぎ回っているようです。
この展示物に限りませんが、国立科学博物館の展示方法の良さが光ります。
恐竜トリケラトプスvsティラノサウルス/地球館B1F
地球館B1Fには、ドキドキして楽しい展示があります。恐竜界のスターであるティラノサウルスとトリケラトプスの全身骨格が、対決するように真向かいに配置されています。
生きていたらどのような戦いが繰り広げられるのでしょうか。ドラマがあります。
近くには、世界一状態が良いトリケラトプスの本物化石があります。この化石が凄いところは、これにより、前脚の甲を(上ではなく)外側へ向けて、親指から中指で大きな体を支えていたことが判明したことです。そのような化石が常設展示で見られるのはありがたいと思います。
今回の紹介は以上です。
さらに親子で楽しく理系脳を育てたい方は、こちらの国立科学博物館監修の絵本がおすすめです。
この記事では紹介しきれませんでしたが、国立科学博物館には日本最大級のアンモナイト化石や鉱物のコレクションをはじめ、月の石、小惑星イトカワの微粒子、進化していないシーラカンス、マンモス、猿人・原人・旧人の復元、クジラ、クワガタなど数多くの興味深い展示がありました。
実際に国立科学博物館を訪ねてみて、ぜひあなたの好きな展示を見つけてください。
最後までお読みいただきありがとうございます。
もしよろしければ、Instagramのフォローをお願い致します!






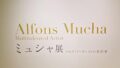
コメント