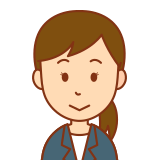
現代アートは難しくてさっぱり分からない…
今回は、そのような人の助けになるように、
東京国立近代美術館にて開催(愛知・豊田市美術館を巡回)されている「ゲルハルト・リヒター展」の鑑賞体験を実例として取り上げます。
現代アートの巨匠であるゲルハルト・リヒター。
彼の作品を観れば、現代アートの深淵を知ることができます。
鑑賞を振り返り、リヒターを理解するためのポイントとなる作品を選びました。
少しでも参考になれば幸いです。
ふりかえる
STEP 0 《1945 年2月14日》(航空写真)
1945年2月14日。この年月日を聞いて、あなたは何を思い浮かべますか。
この作品は、一見するとただのモノクロの航空写真です。
少し離れて遠くから全体を見ると、グレイ色の抽象画のようにも見えます。
一方で、題名への意識から近くで細部を見ると、爆撃の痕跡が具体的に認められ、別の意味を持ち始めます。
さらに、リヒターがホロコーストと向き合った画家という情報を加えると、どうでしょうか。
このように、「ものを見る」ということは、同じ対象であっても何に焦点を合わせるかによって認識が変化します。
STEP 1 《モーターボート》
この作品も、一見するとソフトフォーカスの写真みたいです。
しかし、これは画家の手によって描かれた絵画です。細部を見ると確かに絵画だと見分けられます。
この作品は、元となる写真を正確に複製するように描く、「フォト・ペインティング」の代表作の一つです。
そこに画家の個人的な感情や作為は干渉しません。
この手法はむしろ絵画の特徴を強調します。
つまり、絵画を絵画たらしめるのは、輪郭のボカシや塗料の質感です。
STEP 2 《アブストラクト・ペインティング (CR778-4)》
抽象絵画に「アブストラクト・ペインティング」と名付けられたシリーズでは、筆や刷毛ではなく、ヘラ(スキージ)で描かれていくようになります。
ヘラで描くとどうなるか。
絵の具のコントロールが難しくなり、画家が表現したいイメージをそのままに描くことができなくなります。
このように、リヒターの関心は、絵を描くことから画家の主観を取り除くことにあるようです。
画家の意図がそぎ落とされた実物を見て、人はどうイメージするでしょうか。
STEP 3 「グレイ」と「ガラス・鏡」
画面一面グレイ色の作品。グレイという色彩は、カラーチャートにあるようなあらゆる色の絵の具を混ぜ合わせると生まれます。
リヒターはグレイについて「なんの感情も連想も生み出さない」「”無”を明示する」と語っています。
一方、ガラスや鏡は、それ自体はただの平面で何も意味を成しません。
観察者が見ることによって、観察者含め物体の”虚像”が写り込むことによってイメージが生まれます。
最後に 《ビルケナウ》
以上のキーポイントを押さえた上で、本展のメイン展示である《ビルケナウ》を鑑賞してみてください。
あとは自分の目で、自分の身体で。
この展示空間は、アウシュビッツ・ビルケナウ強制収容所で囚人が隠し撮りした写真のイメージの上に描かれた4点の巨大な抽象画《ビルケナウ》の実物があり、
対面の壁にその同寸の複製写真、さらにそれらの間に、観察者が見ると自身と作品が写り込むグレイの鏡が設置されています。
それぞれのイメージから心がどんな働きをするでしょうか。
(私は震えが止まらなかったです。)
今回はここまでになります。
最後まで読んでいただきありがとうございました!
Twitterのいいね・フォローよろしくお願いします!







コメント