美術館へ行って心を癒そう!本日の展覧会はこちら!
「日本画革命 〜魁夷・又造ら近代日本画の旗手」
展示作品がすべて福田美術館所蔵(新たに所蔵した旧・山本憲治コレクション)なので、近代日本画を特集した福田美術館のコレクション展としての性格も備えた展覧会です。
福田美術館は、日本画を中心に所蔵しています。観光客で賑わう京都・嵐山にあって、比較的静かな時間を過ごすことができる、おすすめの美術館です。
眺めのいいミュージアムカフェも併設されていて、カフェやランチの場としても利用もできます。(入館者専用)
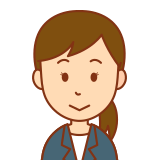
日本画に詳しくないので、鑑賞を楽しめるか不安です……
いくら混雑を避けたいからといって、楽しくなければ時間を損した気分になりますよね。
そこで今回は、私の体験をベースに、「初心者でも楽しめる福田美術館コレクションの日本画家とその作品」をお教えします。
この記事を読むことで、福田美術館が所蔵する画家や作品の特徴がつかめるので、福田美術館での鑑賞をより充実させることができます。
結論から言うと、その画家と作品はこちらです。順番に説明します。
初心者でも楽しめる福田美術館コレクションの日本画家とその作品

横山大観/菱田春草《飛泉》1901年頃(福田美術館蔵)
2つの滝。それぞれが感動した所を見事に表現しています。
横山大観の滝は、高い所から真っすぐに水が流れ落ちる様子を捉えていて、勢いのよさを感じさせます。鳥が空中を飛んでいて、動きがあります。岩肌の形はぼうっとしていて、あくまで滝の直線的な姿が強調されています。
一方、菱田春草の絵は、滝壺の水煙で霞む空気を描いていて、落ち着いた雰囲気があります。鳥は岩の上に止まっていて、静かに時間が流れています。岩は陰影をくっきりと描いて、どっしりとした存在感があります。
1つの画題に表れたそれぞれの感性。好みは分かれるでしょうが、どちらも素晴らしい作品には違いありません。本人が感動した部分を表現することが、人を感動させることにつながっているのです。
小林古径《撫子》1931年(同)
月と撫子。描く素材はたったの2種類で、究極に切り詰められています。それなのに、というよりだからこそ、心を動かす力があります。
明るい月はより大きく、可憐な撫子はより純白に。互いに影響し合うように、特徴が際立っています。そんな2つの関係に、見る者も惹きつけられます。要らない要素を引き算する、小林古径の見事な構成力です。
山口華楊《待春》昭和時代(同)
巣穴で冬を越すウサギ。この絵は物語性があり、心を動かします。
ウサギは、体を丸めてどこか一点を見つめ、寒さを耐え忍んでいるようです。雪には穴が空いていて、雪解けが始まっています。地面から赤い芽が出てきました。
春までもう少し。「がんばれ」と思わず応援したくなります。つらい冬を生き抜くウサギの物語です。
山口華楊は、竹内栖鳳、西村五雲に続く京都画壇の画家で、やはり動物画を得意としました。
(京都画壇についてはこちらの記事もどうぞ)
- 京都画壇について:【京都市京セラ美術館】
- 竹内栖鳳について:【特別展 竹内栖鳳】
- 西村五雲について:【京都国立近代美術館】
東山魁夷《緑の朝》1991年(同)
まもなく夜が明ける池畔。青い色彩が画面全体を支配しています。
このような落ち着いた深い青は、東山魁夷に固有の色です。つまり、一目で彼の作品と分かる特徴です。
物静かな色で、心と対話する時間へと連れていきます。水面に上下反転で映る景観は、まるで内面を映す鏡のようです。
その人にしかない色は、その人の世界へと惹きつける力があります。自分だけの色を見出すことが、表現者にとって大事なのです。
加山又造《雪ノ朝》昭和時代(同)
明るい空にそびえ立つ雪山。型にはまらない日本の冬の美しさが表現されています。
冬の表現にありがちな風雅な感じではなく、キリッと張り詰めた冷気を感じます。山肌の模様が毛細血管のようで、自然の摂理の複雑さを与えています。
たしかに冬は、よく晴れた日の、厳しくも透き通った空気にも趣がありますよね。加山又造の作品は、独自の美意識を貫いているからこそ、はっとさせる力があります。
今回の紹介は以上になります。
最後まで読んでいただきありがとうございました!
Twitterのいいね・フォローよろしくお願いします!
[参考文献]
辻惟雄(2021).『日本美術の歴史 補訂版』.東京大学出版会








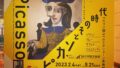
コメント